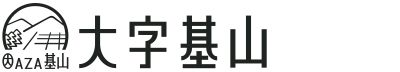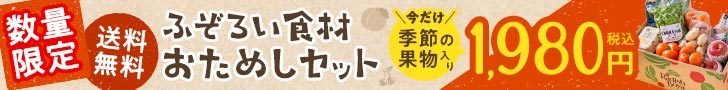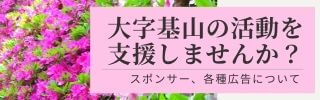写真で「きゅん!」命がけ?2年に1度・上峰町”米多浮立”の天衝舞
基山町から車で約30分の佐賀県上峰町に、江戸時代から伝わっているという「米多浮立」があります。
浮立は、九州北西部に伝わる、農民の素朴な願望と感謝を表現した伝統芸能。
米多浮立はそのうちのひとつで、佐賀県重要無形民俗文化財にも指定されています。2年に1度、老松神社の秋祭(10月下旬の土日)に五穀豊穣と無病息災を願って奉納されます。
2025年は奉納の年でしたが、諸般の事情で2026年10月24日・25日に延期されています。

巨大な被り物が米多浮立ならでは!
米多浮立の一番の特徴は、頭に高さ3メートルの「天衡」と呼ばれる角のような被り物をかぶって舞う、というもの。太平洋戦争中に途絶えたものの、戦後に復活し、昭和46年には保存会が結成され、今日まで受け継がれています。
巨大な天衝の総重量は、およそ7kg。舞人の頭頂部に装着するには、複数人の手助けが必要です。
毎年、天衝を修復する際に和紙が重ねられ、この重さになったとか。

7kgを頭に乗せる舞人は3人
天衝舞役は3人。3つの天衝にはそれぞれ「日」「月」「宝珠(星)」が描かれていて、近くで見ると細やかな龍の絵柄にきゅん!

笛や太鼓に合わせて舞います
天衝を両手で支えて、笛や太鼓の音に合わせて片足を上げて舞う、その力強い姿ったら!

踊るだけでなく、大太鼓も叩く天衝舞

重力に負けない運動量とスピード感
太鼓を叩いたり、時々「首、大丈夫!?」と心配になるほど前かがみになって、体全体で回転したりとハードな天衝舞。
危険も多そうですが、地元の方にとってこの役はお祭りの花形なので誇らしいとのこと。息を切らして休憩をはさみつつの舞は、本当に見応えがあります。
天衝舞で気になるのは巨大な被り物だけでなく、舞人の腰周りにセットされたゴザ。

座れるサイズのゴザの謎
保存会の方にお聞きしたところ、昔は太鼓を打ち誤った時にすぐに切腹ができるよう、腰に短刀とゴザを付けていたそうで……。
現代は短刀の代わりに短い棒を腰に差していますが、ゴザはそのまま受け継がれています。天衝舞を奉納する行為そのものが、昔から「命がけ」だったんですね。
米多浮立は、伝統的な衣装で着飾った地元の少年や振り袖姿の少女たちも、それぞれ楽器を持って演奏します。

子どもたちの衣装にもきゅん!

長年使い込まれた「ササラ」
中でも、少女たちが木をすり合わせて拍子をとる「ササラ」は、地元の保存会などで大切に保管され代々受け継がれてきた伝統楽器です。

上峰町内の灯籠にもきゅん!
2023年の取材時、町内の各家庭には、かわいい御神燈が門のところに飾られていました。昔はこの中にろうそくが入っていたとのこと。

神社の細部にもきゅん!できます
佐賀県内で現在、伝承されている民俗芸能は約200余で、そのうち約160余が浮立だそう。
浮立には、他にも「面浮立」「行列浮立」があり、各地域でさまざまな形で発展し、伝統行事として受け継がれています。
佐賀県上峰町「米多浮立」
イベント概要
- 日時:2026年10月24日(土)・25日(日) ※2年に1度、10月下旬の土•日の秋祭り
- 場所:米多老松神社(佐賀県三養基郡上峰町前牟田1409)
- 2025年開催予定が、2026年に延期になっています
お問い合わせ
- 上峰町教育委員会 文化課
- TEL: 0952-52-4934